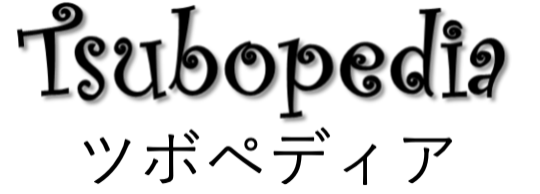PL設変自動つなぎシステム
システム概要
設計BMから、製造BMへ行われる構成情報のつなぎデータの一部を製造BMに、自動更新するためのシステム。主な処理はメインフレーム上にて、バッチ処理される。導入は、2000年に、分社化前のMMC 乗生情シ部 開発Gによって行われた。自動更新されたデータは一旦仕訳用DBに保存され、ユーザーの確認後、DBに登録される。
導入の背景
デイリーで設計部門から設計変更データ(以下設変データ)が接続されているが、製造側のPL設変つなぎ処理では設変対象部番等をリスト出力するだけで、PPLへの設変反映作業は100%ハンド作業である。 設変データをシステム的に有効利用できないのはEPLとPPLで構成に差がある為で、機械的に接続するのは 困難とされてきた。
しかし、製造BM再構築でKD形態コード゙、シンボル次工程を適用したことにより、KD出荷単位の違い、生産ライン の違いで製造側のPLライン、VCを増幅することなく仕訳が可能となり、さらには、設計段階で製造の構成を 考慮することにより、EPLとPPLの構成がより近くなる。 そこで今回、PL設変データをPPLに自動反映すべくPL設変つなぎシステムの改善に着手する。[1]
処理概要
PL設変つなぎデータのVC追加、構成追加、変更、削除データを製造BM PPLに反映する。 設計から接続されるPLNO(EPL上、設変対象部番をもつPL) について、製造BMの該当PLに設変処理を行う。設変処理した結果は、基本的にPL仕訳DBに登録して、ユーザの確認後BMに反映することとする。
関連項目
出典
- ^ PL設変自動つなぎシステム 基本設計書